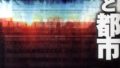史実に基にしながら、どう考えてもフィクションという魅力
慶長五年(1600年)。小説の舞台は南部八戸(はちのへ)。
八戸氏二十代当主、南部直政の妻である祢々(ねね)は、夫と息子を相次いで亡くし、自らが城主になることを決意する。
史実を基にした、江戸時代唯一の女大名が主人公の歴史小説。と、思っていたら……。
(いや、実際にその通りななんだけど。)
プシュッ、プシュッ!ボエッ、ボエッ!と登場。偶蹄目ウシ科。なんとも奇想天外、語り手は羚羊(かもしか)なのである。
「我は片角なり。我が言葉を聞け」
南部の秘宝、呼び名は『片角』『一本角』『叱り角』
羚羊(正確には一本の角)によって語られる女大名の一代記。
しかもこの羚羊さん、なかなかユーモアのセンスをお持ちのようで、人間たちの営みを俯瞰し、普通に語っているだけでクスクスと笑わせてくれる。
いわゆる神の視点。全てを知っているモノによる昔語りは、ゆるやかに続くエピローグを読んでいるかのような心地よさ。
無垢で可憐な乙女のころから、煙管が手放せなくなった晩年まで(罵詈雑言を吐いても魅力的)。
なぜか物の怪(もののけ)たちに慕われる祢々さま。
次々と降りかかる困難、宗家からの理不尽な要求。
知恵を絞り、戦を回避し、いつしか嫌っていたはずの諜略に長けてしまうという皮肉。
自らの信念を貫き通し、また十分すぎる犠牲を払ったその生涯。
時々登場する物の怪エピソードが無かったら、悲しいことが多すぎて読むのが辛かったかも知れない。
しかし、民話や言い伝えや怪談の類、現実と非現実が物語の中で混ざり合うことによって、読み心地は決して悪いものではない。
実在した人物たちを登場させ、史実に対しても忠実ながら、どう考えてもフィクションというのが『かたづの!』の魅力。
個人的には歴史小説としても十分楽しむことができたし、意外と現実的な物語なのでは?という印象すら受けたが、リアリズムの小説を好む人にオススメしていいのかは微妙なところである。
しかし時は江戸時代。だれも「非科学的だ!迷信だ!」などとは言わないであろう。むしろ当時の人々の怪異に対するスタンスは、結構この小説くらいがリアルだったのではないか?と思ったりもする。
いったいこの物語は、軽いのか?重いのか?
よくわからないけれども、とにかく良い塩梅であること間違いなし。
小説全体を通して感じる、優しさというか柔らかさのようなものを、ひらがなの『かたづの!』というタイトルがよく表している。
青森県八戸。岩手県遠野。
旅行に行きたい土地がまた増えてしまった。
もちろん、河童も登場します。