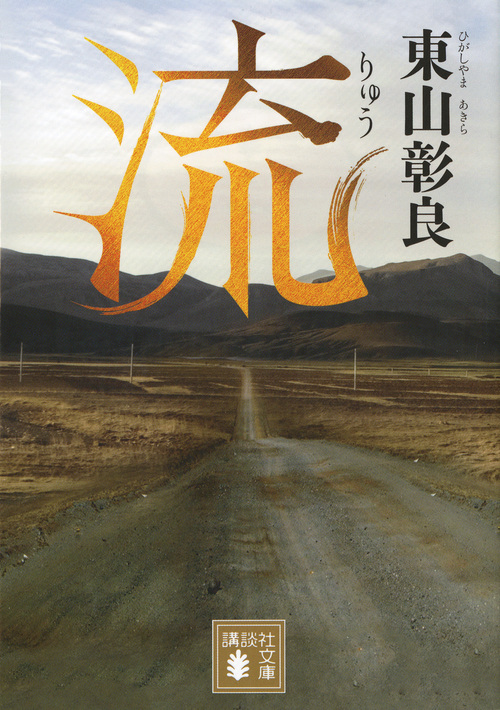混沌の時代と土地の記憶を辿る、青春小説の傑作
舞台が台湾ということで、読みづらいのかな?と少し心配していたけれど、まったく問題なかった。軽々と国境を越えて、作品の世界に入り込むことができる。
笑えるエピソードも多く、プロローグから下品な大陸ネタで楽しませてくれる。
国家の歴史と、家族の歴史。友情、恋、そして生命の物語。
犯人探しというミステリーを用いつつも、基本的にはストレートな青春小説。しかも、ただ面白かっただけではなく、読み終えた後にも確実に何かが残る。
文学的なテーマを持ったエンターテインメントとでも言うのだろうか?
これだから小説はやめられない、そんな気分にしてくれる。
やはり、そこに深みをもたらしているのは、重要な登場人物である、主人公の祖父を巡る物語。
孫が辿る家族のルーツと、祖父が生きた生涯。
たまたま飯を食わせてくれた方に味方する。こっちと喧嘩しているからあっちに味方する。
戦争と混沌、共産党と国民党。そこに大義など無かった、と語る祖父。
戦争で人を殺した祖父の世代は、善だったのか?悪だったのか?という、おそらく明確な答えの出せないであろう、とてつもなく大きなテーマにも取り組んでいることを、ひしひしと感じる。
当然『流』では、人間の弱さや醜さなどが正面から描かれることになる。
また、それが作品全体に何とも言えない緊張感を与えている。
しかしそこには、深刻だからこそ必要なユーモアとアイロニーがあり、その結果として登場人物たちのチャーミングな魅力がある。その辺のバランスの取り方は見事としか言いようがない。
バランスと言えば私が特に気に入っているのは、リアリズム小説の中になぜか所々で現れる、狐火や鬼火、幽霊や予言の類。これらが違和感なく物語に溶け込んでいること。
スピリチュアルな本で、その手の話をされてもあまりピンとこないけれど、『流』の場合は土着的とでも言うのだろうか?戦争で人を殺したことのある年寄りや、やくざ者たちが、神や幽鬼を恐れ、敬っているその姿。
罪悪感が根底にあるせいなのか、その信仰らしきものには、不思議な説得力がある。
お婆ちゃんとの約束を破ったことによって、不運に見舞われたのなら、それはスピリチュアルでも何でもなく、ただ単に当然のバチが当たったのである。
そんな空気が小説に馴染んでいるのが、とても印象的だった。
素敵な青春小説の中に、不思議と調和する重さや暗さを持つ『流』という傑作。
良いことも、悪いことも。全てひっくるめての人生。
そして、それはこれからも続いていく。