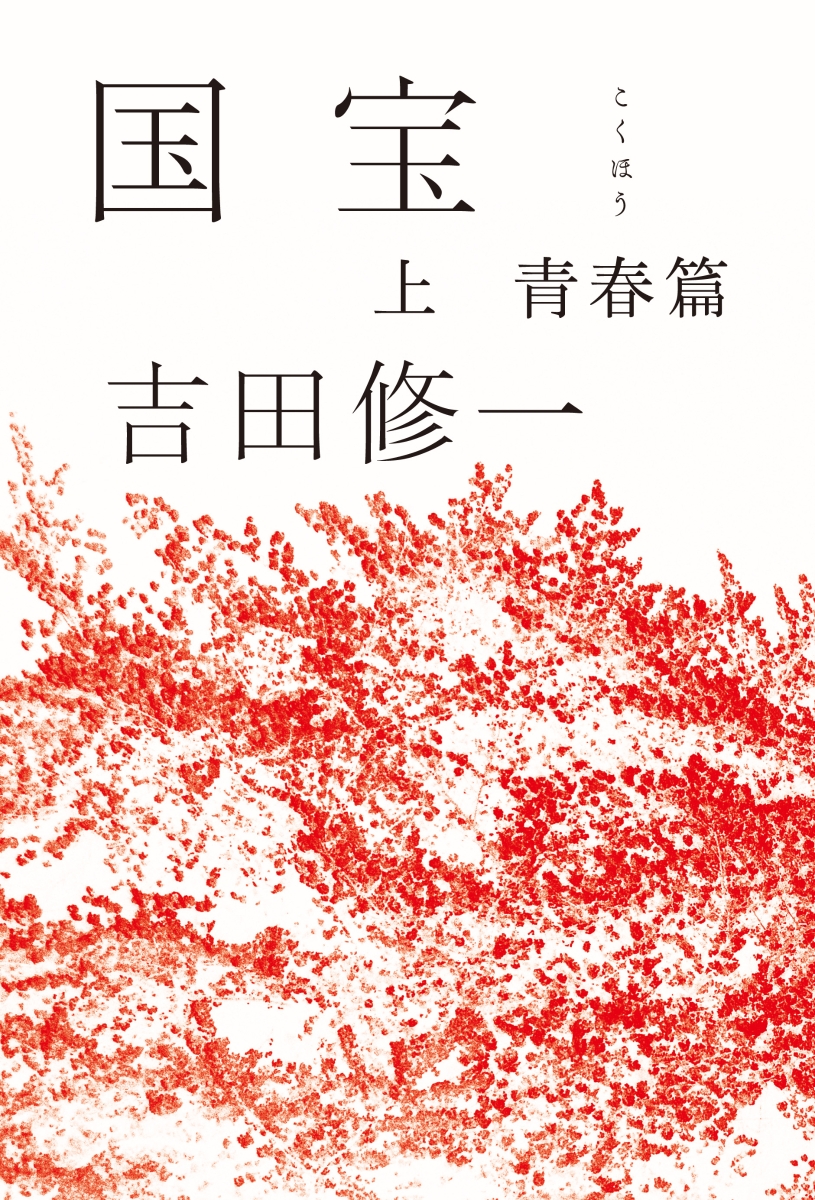読者ではなく、観客になっている
『国宝』を読みながら、はっきりとそう感じる瞬間が何度もあった。
とにかく舞台のシーンが素晴らしい。
二人の歌舞伎役者の人生と、その周囲の人々についての物語。
青春篇、花道篇の上下巻。
若き日々から老境まで、というタイプの長編小説には、やはりテンポの良さが必要だと思う。別の言い方をするとエピソードを端折る、というテクニックも重要になってくると思うのだけど、『国宝』では年月の経過の仕方がとてもスムーズで心地良い。
その辺りについては、語り手の存在が大きいかと。
この小説では、語りというよりナレーションと言ったほうがピンとくるような気がする。パッと浮かんだのは、大河ドラマや連続テレビ小説のイメージ。
著者と読者の間にいる、物語には直接タッチしない人物(上品な年配の女性、と私は想像した)。
彼女の丁寧な言葉で語られる長いお話を、読みながらも聞いている。そんな感覚だろうか?
数十年という長い期間、登場人物たちを追いかけていくわけで、はじめの頃からは想像もできなかったような、彼らの関係性の変化を見届けることにもなる。
極端な浮き沈み。時間だけが解決できる問題。取り返しのつかないこと。
『青春篇』で多くの人物にがっちりと心を掴まれている。だからこそ揺さぶられる。彼らを身近な人間のように感じたり、心配したり。そんな気持ちになるのも長編ならではの魅力。
また、『国宝』の舞台で演じられる演目、このあらすじも見逃せない。
古くからある、型としてのストーリーが持つ普遍性。
喜久雄と俊介が演じている内容と、ふたりが歩んできた人生との重なり。
メタファーというほどの共通点はないけれど、思いを馳せる、このくらいの距離感が個人的には好みである。
演じる為のバックボーン。役者本人から滲み出るもの。
この小説に登場する役者たちの、芸に打ち込むという姿勢にはとにかく圧倒される。すべてが芸の肥やしであり、すべてが芸に直結する。
他のすべてを犠牲にしてでも……。
そんな硬派な面とは対照的な、昭和歌謡的、ワイドショー的な側面があることも、エンターテインメントとしてぐいぐい読ませるポイントになっている。
いつの時代も、天才やカリスマたちが、周囲の人間にとって善であったかと言えば、多くの場合それはノーである。
しかし魅せられた人間というのは、尽くし、差しだしてしまうもの。
古く、狭く、閉じている。伝統芸能という男性的な世界。
それを支える周囲の女性たちの凛とした姿。役者の女房としての生き様も強烈な印象を残す。
明らかに男より引いた位置に立つ女という、現代からすると明らかに古い価値観。
そんな世界で二人の男が演じているのは女形であり、女性の心、情念や美しさを表現し、踊っているという構造がとても興味深い。
女形というのは男が女を真似るのではなく、男がいったん女に化けて、その女をも脱ぎ去ったあとに残る形である。
波乱万丈の道を歩み続け、狂気とも言える芸の高みにまで上り詰めた時。
そこからは、いったいどんな景色が見えるのだろう?