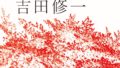いわゆる【日常の謎】と呼ばれるタイプのミステリーであるけれど、その日常の舞台が戦場であることが本書の大きな特徴。ライトなのにヘビー、そんな少し変わった読み心地の要因でもある。
第二次世界大戦時。ナチスドイツ占領下である西ヨーロッパへの、連合国による侵攻作戦。
おそらく多くの人が、【ノルマンディー上陸作戦】として知っていると思う(本書は海からの上陸ではなく同日の降下作戦から始まる)。また、ミリタリー系のリアリティを追求しすぎてマニア向け、なんてことも無いので、戦争ものをあまり読まない人も楽しめる小説だと思う。
ちなみに日本人はひとりも登場しない。
合衆国陸軍、第101空挺師団第506パラシュート歩兵連隊、第3大隊G中隊の管理部付きコック、ティモシー・コール5等特技兵。
プロローグでは、軍隊における名称でつまづいて、挫折しかけたけれど……。
しかし、複雑な所属部隊名の仕組みを、国、州、市、町に例えて説明し、さらにそこから学校、クラス、最後には給食当番!という言葉まで使ってくれたおかげで、主人公がどこに所属していて、何をする人間なのか、完璧に理解することができた。
これで読書のスイッチが入って、どんどん物語に夢中になる。
仲間から「キッド」と呼ばれる主人公ティムが、まだ頼りなかった頃は、日常の謎と言えるギリギリのラインを保っていた。
しかし、中盤あたりから戦況がシリアスになってくると、日常の謎もまったく別の様相を見せはじめる。このあたりの凄みというか、感覚の変化を是非とも味わっていただきたい。
連作スタイルを用いた小説だと思っていたので(というか実際に内容もそうなっているんだけど)、予想以上に長編小説ならではの満足感を得られたことが嬉しい。
というか、このスタイルを使ってきっちり長編として読ませるのは、なかなか難しいことだと思う。
進軍の行程、戦況の変化、主人公の成長など、いろいろと重なっての結果だと思うけれど、ひとつの物語という印象が強い。
いとも簡単に死んでいく人間や、戦争神経症など、いくらでも暗いストーリーになる要素のある中で、ティムの人の好さや、仲間との友情が大きな救いとなったのは間違いない。
『戦場のコックたち』と言うくらいなので、それなりに美味しそうな料理、調理法の描写があるけれど、個人的に印象に残った食べものが、たびたび登場する糧食(レーション)と呼ばれる携帯食と、何と言っても粉末卵である。
とても不味そうなんだけど、読んでいるうちに無性に食べてみたくなるのは、舞台が戦場だからなのだろうか?
戦場のコックたち 深緑野分