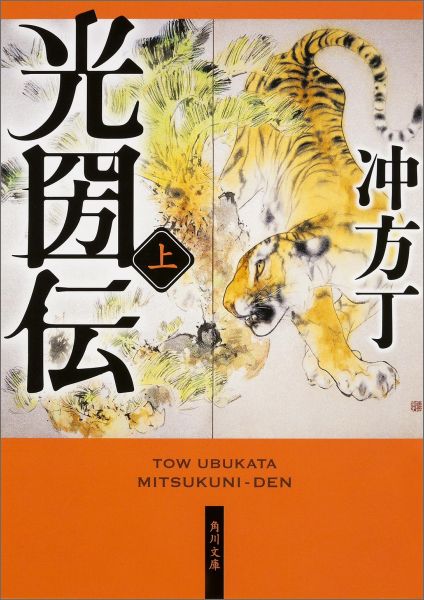光圀は優しく囁きかけると、膝下に捕らえた家老たる男を、ぶつりと脇差しの刃で刺した。
序ノ章より
出だしから、なんとも物騒なご老公さま……。
子どもの頃にテレビで見ていた『水戸黄門』のイメージは、『光圀伝』によって粉々に打ち砕かれた。
ネタバレでは無いと思うので書いてしまうと、印籠も出てこないし、「この紋所が云々」といったセリフで皆がひれ伏す、なんてことも一切ない。
『光圀伝』は私のような歴史オンチほど、より多くの驚きを味わことのできる小説である。
京の文化人を唸らせ、詩で天下を取る
ん?いったい何を言っているのだ、この男は?
剣の修業はしないのか?と。
このあたりで、私が想像していたような物語ではないことに気付く……。
関ヶ原の合戦から四十年が過ぎ、泰平の世を迎えた日本。
戦を知らない世代、浪人たちで溢れかえった江戸の町を闊歩する、若き日の水戸光圀。
容姿端麗、文武両道にして、傍若無人の傾奇者(かぶきもの)。
もし、戦国の世に生まれていたならば……。そんな若者が抱えるフラストレーションがひしひしと伝わってくる。
誰とも剣を交えない、というか明確な敵がいない。
にもかかわらず、感じるのは剣豪小説のような雰囲気。これは一体どのようにして作り出されているのだろうか?
もちろん、光圀の個性によるところも大きい。優れた知性と強靭な肉体。まっすぐな性格。野心に満ちた若者の成長物語としての魅力。
しかし、それだけではない。
個人的に感じたいちばん大きな要因は、この小説には確固とした決まりごとがあるということ。
「不義を義に立ち返らせる。まさに中道。まさに大義だ」
義であるか否か?是か非か?
これこそが作中に何度も繰り返し登場するキーワードであり、小説内におけるルールである。
この時代の人間の死生観や、家名、血筋、名誉、婚姻に対する考え方。
これらを受け入れられるかどうか、読者としての判断基準はいたってシンプル。すなわち、ストーリーが面白いか?引き込まれるか?
そうして、一度中に入ってしまえば、そこは光圀が生きた江戸時代。
ルールは志となり、剣の代わりに詩文があって、戦の代わりに大義がある。
親子の葛藤、兄に対する負い目、生涯の朋友、妻の存在。
特に兄弟の絆は胸に響くものがあった。
その個性に隠れがちであるが、兄にみせるその弱さもまた、光圀という人間が持つ資質。
自分の力だけではなく、人によって活かされてもいる。
だからこそ、周囲の登場人物が魅力的に映り、そんな彼らの言動を通して光圀の個性が輝きを増していった印象が強い。
物語を読み終えての感動と共に、かすかに残る憐みや苦い感情。大義がもたらした悲しみ。
ルールやシステムは、時代や場所の変化によって、善悪の基準ごとひっくり返ってしまうような、危ういものである。
そんなことを考えさせられる小説でもあった。