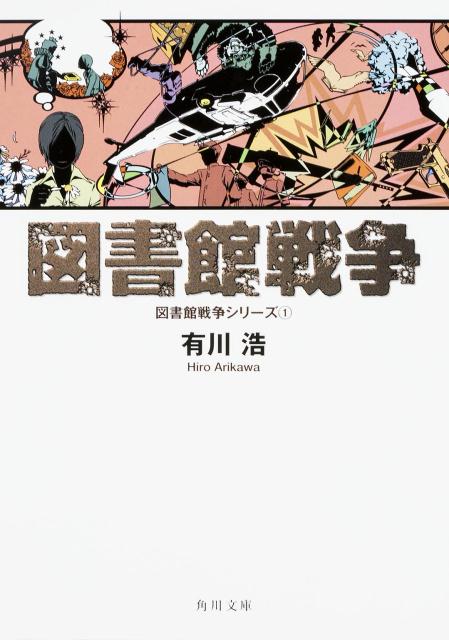本好きへのご褒美のような小説
公序良俗を乱し人権を侵害する表現を取り締まる法律、メディア良化法。
検閲が合法化されて、言葉と本が狩られる国になった日本。
狩られた本が確実に読める場所として価値を高め、本を守るための武力を持つに至った図書館。
これだけ聞くと近未来SF、ディストピア小説のようだが、実際に『図書館戦争』を読んでそのように感じる読者は、あまりいないのではないだろうか?
スケールが大きくて突拍子もない話だけど、身近なエピソードに落とし込むことによって、違和感なく私たちが暮らす日常の延長として読むことができる。
個人的には設定がリアルというより、ストーリーの面白さが問答無用にリアリティを生み出している、という順番のような気がする。
こだわるところは細部まで徹底的に描写しつつも、難しい言葉は使わず、無駄な説明もしない。
専門家なども納得するような隙の無さだと、確実に読みやすさは落ちることになるので、エンターテインメントとしては絶妙なバランスの作品ではないだろうか?
有川浩は雑誌の対談で、
「作家にとって一番大事な作業は、膨大に調べて膨大に捨てること」
「調べたことの9割は捨てている」
とまで言っている。
だからこその、読みやすさではないだろうか?
下地がしっかりしているからこそ、登場人物の魅力が際立つのだと思った。
有川浩の小説を読んでいると、小説家がたまにインタビューなどで語る、登場人物が勝手に動き出す、ということがすごく実感できるような気がする。
読者としては特にすることはない。お気に入りのキャラクターを見つけて(必ず見つかるはず)、物語の世界にどっぷりと浸かればいいのである。
あっという間に読み終わってしまうはず。
そして、続きがあと5冊もあるとわかった時の幸福感……。
ミステリーと文学しか読まなくなった私が、エンタメや恋愛小説からライトノベルまで、幅広ジャンルの小説を再び読むようになったきっかけがこの『図書館戦争』である。
ただ面白いから本を読むという、シンプルな喜びを与えてくれる。
緊張感のある攻防、派手なアクションに知的な頭脳戦。
同時に個人的には絶対使わない言葉である、胸キュン、ツンデレな展開にドキドキしながらラブコメを楽しむ。
カッコいい大人とは?
筋が通っているってこういう事なんだ!
そんな硬派なところも魅力的な小説であった。
久しぶりに文庫版で読み返してみると、表現の自由という問題に関して、単行本出版から十年以上を経て、現代の日本が『図書館戦争シリーズ』の世界に近づいてしまい(共謀罪、差別、ヘイトスピーチ、元少年Aの手記問題など……。)、小説のリアリティが増すという結果になっているような気がする。
いくつかのエピソードは、予言の書のような趣さえ帯びてきて、初めて読んだ時とはまったく違う印象を受けた。